こんにちは。今日は今更ながらのこちら。アドラー心理学を日本に広めた1冊と言っても過言ではないかもしれない、かもしれない大ヒット作です。ですがですが。早速行ってみますか。ところでいや~、時節の挨拶ってのも大事なんですよね、いつも『こんにちは』で芸が無くて済みません。ほんと、こういうのって普段からの練習が必要なんですよね。とはいうものの行ってしまうのでした。
これまたきっと超訳だ。
自分の語学力の無さが悔やまれるのですが、すいすい読めるなら。とはいっても内容がないようなだけに語学力だけでは理解しきれないと思うのですが、それでも読めるなら、原作に挑戦した方が良いと思う1冊でした。
アドラー心理学を紹介する、というコンセプトで止めておくなら文句はないのですが、本作はもう1歩余計に踏み込んでいる感じがあり、その1歩が多分、多分ですよ、原本とずれています。アドラーが言いたいことではなく、アドラーの言いたいことを学んだ作者の意見になっていると思われます。言ってみれば『超訳』。吉田松陰の本のあれですね。
いや、良いんですよ。古文にせよ外国語にせよ、それなりの勉強をしてこなかった僕(ら)にとっては現代日本語訳していただけるのは本当にありがたい。以前にも何度も書いていますが、文化的な背景が時の流れとともに変化しているのでそのままでは汲み取れない部分って絶対あって、そこを解説してくれるのは大変助かります。
ですが、これにはこれで程度というものがあって、そもそも訳するのはその人なり作品なりが好きな人なので、原作に対するご自身の価値観みたいなものが滲んでしまいます。場合によっては、というか、吉田松陰の本やこの本の場合、好きすぎたんでしょうね。ご自身の意見がかなり前面に出てしまっていて、おそらく原作で言わんとしていることとずれているんじゃないかと思います。・・・と、原作を読んでいない人間がほざいております。
この手の哲学とか心理学とかはとにかく解釈が難しいというか、自分の中にそれを落とし込むことがとても難しいジャンルですのでほんと、文句を言うのは罰当たりなんですが、原作の直訳も欲しいです。そういう意味では以前読んだ五木寛之さんの『私訳 歎異抄』はバランスが良かったと思います。読んだときはこんなもんか、と思いましたが、この手のを何冊か読んでいくうちに、五木さんの歎異抄との、あるいは親鸞、唯円の各上人との距離の取り方のうまさみたいなものがよく分かってきました。
中身について。みなさん大好き「要するに」のはじまりです。
はい。要するに、周りの課題と自分の課題をきちんと分けられないから苦労するんだ、と。人の苦労までしょい込むことはないよ、と。また、これで良いのか迷ったときは「それが世のため人のためになっているのか」を判断基準にしろ、と。これを頭において、今に集中しろ、そしてその成果を評価しよう、と。こんな感じですかね。過去も未来も関係ないあたりは禅の話にも出てきますが、それに触れてないのがかえって怪しくも、アドラーもそういうことみたいですよ。
あと、本作によるとアドラーは因果関係を逆に考えているようです。
多くの場合、原因があって結果が出ると考えるかと思いますが、本作によると結果を出すために原因を見出す、というか作り出す、と考えるようです。ある部分では納得できますが、説明はしきれないかと思います。うまい例えはできませんが。
また、縦の関係、横の関係、というそれぞれについてはいくらか分かりましたが、それを絡ませると先の結果を出すために~っていうのがごちゃごちゃしてきてしまって僕は正直ギブアップです。タイトルの『嫌われる勇気』についても、みんながそれを知っていれば何かが変わりそうですが、そうでない場合は単に敵を増やして終わるだけ、なんてことになりそうで、よっぽど精神力が強い人でもない限り潰れてしまうように思います。読んでて苦しいところでした。
カントだのユングだのデカルトだの(?同じ人いないか?)と名前だけなら聞いたことがある人々と肩を並べる学者、と聞いていたし、寄り添うタイプの論の持ち主だと思っていたのに、結構厳しいですね。もっとこう、優しく包み込んでくれるような教えが欲しかった、というのが正直なところですが、これじゃ宗教に行っちゃうかな?それはそれで深入りせずに済ませたいというのも本音です。読書感想文くらいでちょうどいいと思いました。
それでも励みになる言葉。
「我々は馬を水辺に連れていくことはできるが、水を飲ませることはできない」だったかな?言わんとしてることは受け取りました。手助けはできるけど、決定的なことは自信でやってもらうほかない、ということですね。サッカーに例えるなら、決定的なラストパスなら出してやるけどシュートを決めるのはお前だ!みたいな。励みにはなる言葉ですよね。
言わんとしてることは分かるんですが、そこまで寸止め出来るなら最後までも出来ちゃうでしょ、本当は、って思うわけです、僕は。どうせならそこまでやってよ、と。で、違和感。自己肯定感を感じさせたいのかしら。
そうだ。
そういえばですよ。非常に刺さったのが『承認欲求を否定しろ』。です。耳が痛い。激痛だわ。これですよ。図星です。僕はこれが確かにとても苦しい。誰かに認めてもらいたい。存在を肯定してもらいたいもん。感謝されることと認められることが違うっていうのは分かりますが、感謝でもいい、肯定でもいい。とにかく優しくされたいのよ。でもそのために無理して本来の自分と違う方向に行ってしまうんですよね。相手が求めていることに行こうとしてしまう。
ここで勇気を出すって、多分相当な事よ。おおごとです。で、多分目的論的に原因を作ってしまうんでしょう。でもそれ、仕方ないじゃないですか。出来る場面と出来ない場面、出来る相手と出来ない相手、状況により変わります。それでもその場をしのがなければならないなら相手に合わせるのもやむを得ないと思います。そういう場面が多いなら、自分が去ればいいとか、嫌われる勇気を持って、とかってなるんでしょう。
でも、多くの場合、僕のような人間が辛いとき、そこで背中を押してくれる存在がいないのがまた辛いのです。そういう困ってる場面で水辺に連れて行ってくれる人はいないのです。ここが現実的じゃないというか、きれいごとというか。口先だけの「困ったときには助けてやる」みたいな感じが何とも嫌です。
そしてお決まりの「相手は変わらないのだから、自分(の見方)を変えよう」という考え方。それこそみんながこの共通認識をしてくれないと自分ばかりが負担を負うわけで、これはこれでかなりきついと思います。そこに持ってきて「トラウマはない」。これまたちょっとどうかと思います。トラウマ自体はあると思いますよ。解決できるとかできないとかってところで「解決できないトラウマはない」っていうなら分からなくもないんですが、存在を否定するのはちょっと。
先の例に例えるなら水辺に連れていけば後は馬が飲むか飲まないかを決めるんだ、って事を主張していますが、何て言うのかな、トラウマにより水辺を避けたい馬がいるかもしれないって思いませんか?ちょっと論点がずれるかもしれませんが、「1メートルの鎖でつながれたライオンは何平方メートルの草を食べられるでしょうか」という問いに対する答えで「ライオンは主に肉食で、この時草を食べませんでした」っていうのがあるみたいな感じで、トラウマ、全否定はちょっとまずかったんじゃないかと思いました。
まとめ。もっとちゃんと読もう。
はい、この本は読書感想文に向きません。何周もしなくてはいけません、禁止シリーズとは別の意味でね。それと単語というか、キーワードは正確に把握していなくてはいけません。これは買って手元に置いて何度も読んで反芻する類の本だな。でもそこまでやるなら原作に触れるのがもっとも効果的かと思います。多分これ超訳ですから。アドラーの意見とは違うことを言ってる気がします。予感ですが。悪口言ってるみたいでごめんなさい。でも心にしみた分、何か感じたんですよ。
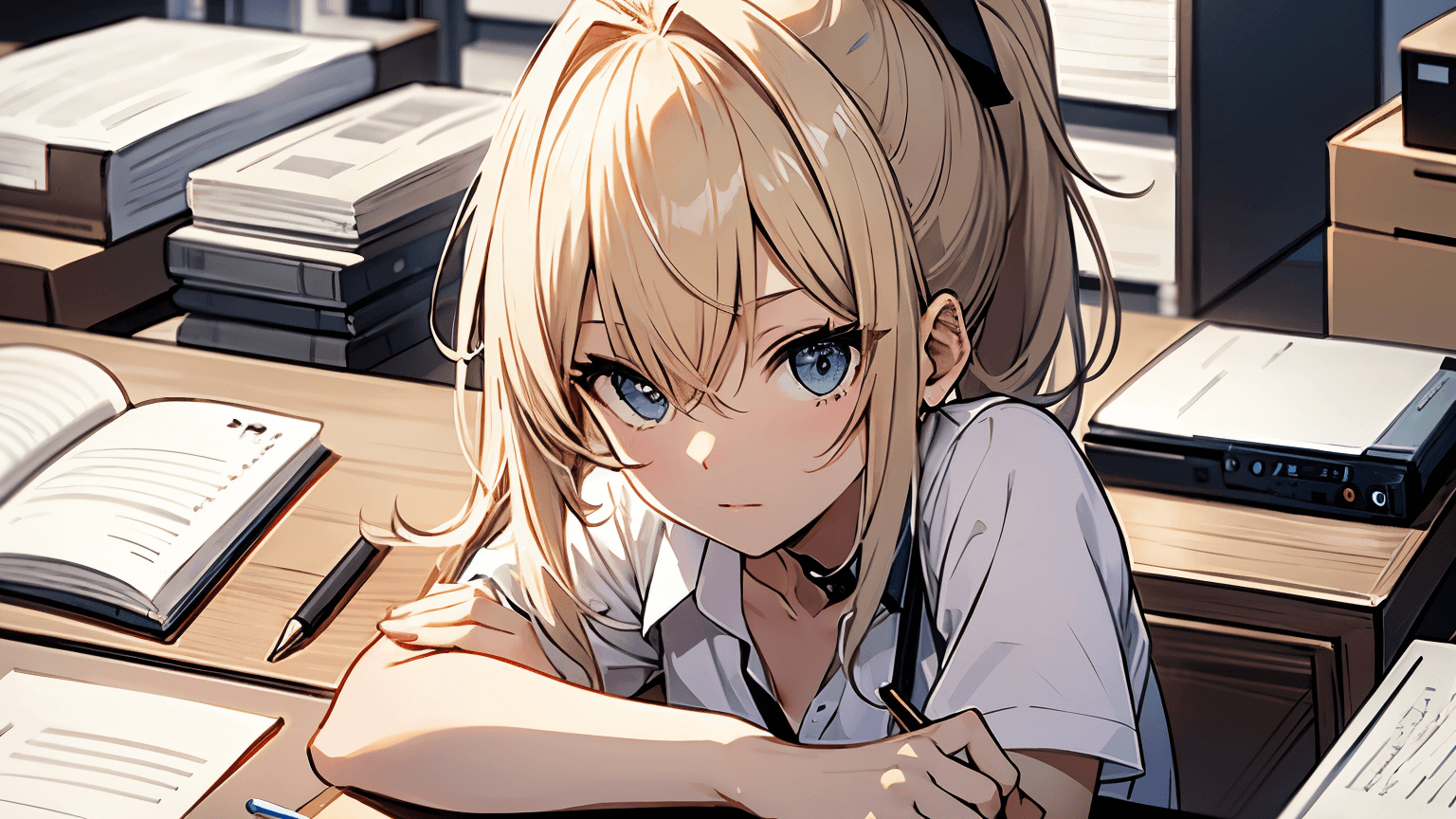


コメント