こんにちは。今日の本はこちら。これもヒットしましたね。歎異抄じゃないけど、何回も繰り返し読みたい本、みたいに紹介されてました。出版禁止の繰り返しとはまたちょっと違う繰り返しですが、こっちの繰り返しの方が良いかな。多くの人には多分こちらを繰り返し読む方が有意義。マニアックな人はあちらを繰り返す方が有意義。
超訳が本当に超で戸惑う。
うん、はい。申し訳ないんですが、訳しすぎというか、著者が吉田松陰の言葉をもとに「私は世の中(主に仕事の場)についてこう思います」と言っている感じがとても強くて、実際松陰の言葉はどうだったのか、それがとても気になってしまったというのが第一の感想です。
昔の言葉を今に持ってきても・・・というのは、仮名遣いとかの文法的なものを除いてなお、文化的な面からも伝わらない部分がある、と以前僕は書いております。それをもしかして読んでくれてたのならありがたいのやら申し訳ないのやらではばかられるものがありますが、あえて辛口コメントすると、この名言系の場合、元のがないと困るのです。元のと、その訳とでセットにしてほしかった。作者の意見はその次ね。原文の役の解説に付け加える感じで書いていただくのが僕的にはベストです。
というのも、時々ぶっ飛んでるんです、名言が。著者の解釈じゃないのか?松陰の意図するところとは違ってるんじゃないか?と思われるものがいくつかあって、っていう割に僕は吉田松陰という人をそこまで詳しく知らない。でも、違和感を感じたなあ。Z世代なのかなぁと若ぶってみたり。
葉隠とかとも関係するかも
読んでて思ったのですが、ここに出てくる言葉、以前読んだ『武士道』、その関連で調べた『葉隠』あたりありきで書かれている感じというか、同じような志のようなものを説いているように思いました。松陰は幕末なので『武士道』とは時代が被ります。葉隠がどうだったか。でも、松陰が葉隠に触れていたとしても不思議じゃないくらい、これらを感じさせるものでしたね。「この本にはこう書いてありますが、」を頭に付けて本作の言葉をつづけるといい塩梅になりそうな。
まあ、割と型破りな人だったっぽいので先人の言葉に斜に構えて、っていうのもありそうではあります。でもきっと読んでる。
塾生は凄いよね。
幕末のスターがたくさんいます。薩長土肥によるその後の日本の支配体制、とあえて書きますが、に多大な影響を与えたことに間違いはないでしょう。そこは本当にすごい。82年ブラジル代表みたい。高杉晋作とか伊藤博文とか久坂玄瑞とか。
あ、僕の幕末には『おーい竜馬』がかなり強く影響しています。山之内容堂はもう悪の権化のような感じだし、龍馬の女ったらしっぷりもここから来ています。武田鉄矢さんがどう擁護しようとも(しかも確か監修か何かでこれにも関わってるような)、福山雅治さんじゃモテてもしょうがないと言われても、龍馬はずるい。
吉田松陰のあり方、松下村塾のあり方がなかなか現代的
っていうか、他がどうかはそれほど詳しくありませんが、おそらくは現代の学校教育に近いものだったのではないかと思われます。当時のよくある秀才のエピソードが『○○をそらんじることが出来た』とかっていうし。
これに対して吉田松陰の松下村塾は塾生の方からお題が出てそれについて一緒に考えるとか、その逆とかもあったんでしょうけど、塾、というより仏教のエピソードに似てるように思いました。仏教って、つまるところそういうものらしいです。暮らしのお困り相談について、ピンポイントにそれに答えるわけじゃないけど、考え方みたいなものを伝授する?宗教らしい。実際修行してないから分かりませんが、何かの本にそう書いてありました。
で、その実践があれやこれやあって、ってことで荒行だなんだと出てくるし、教えの解釈の違いにより宗派が分かれているようです。
ま、話を戻して、おそらくお釈迦様が直接話をしていた頃のスタイルに近い形の塾だったのではないかと思われます。にしても活動期間が短かった。異端児はやっぱり止められなくてやらかして処刑されてしまってね、っていう所はみんな知ってるか。獄中でもあれこれ考えたり塾めいたことをしたりってしてたらしいですよ。これまたキリスト教のイメージでした、僕的には。すごいわこの人。
各宗教のみなさんすみません。多分足りない部分が多く、誤っている部分もあるかと思いますが、本作を読んでの感想の中での僕のイメージですのでご容赦ください。
にしてもだ。
超訳が本当に惜しい。ビジネスを意識しすぎている気がします。吉田松陰的な発想からのビジネスの自己啓発本っていうと結構しっくり。先の繰り返しになりますが、超訳はやめて。って、僕が読まなきゃよかっただけなんですがね。
気になってたんですよ。『できるビジネスマンのカバンの中(だかトランクの中)』が雑誌で紹介されていて、出張とかで移動するときの荷物の紹介なんですがそこにこの本があったもんで。たまたまか?って思うでしょ?でも違うんですって。その人が持ち歩くのは繰り返し読む本なんですと。新しいものに触れるんじゃないんですね。
僕は逆で。って書いてて自分は『できないビジネスマン』っていうこと?なんて寂しくなってしまいました。そんなことない。大丈夫。自己肯定感。僕の本の持ち方だってきっといいはず。では発表しますと、僕は逆で、必ず文庫本を1冊は買うんですが、それは必ずって言っていいくらい、その電車なり飛行機を待っている時間に買います。本選びも旅の一部なんですよ、僕にはね。だからその時のテンションなんかがかなり影響するしやっぱり目に付く平積みの中から選ぶことが多いのですが、選ぶことも楽しみで、とりあえず現地調達してます。悪くはないでしょ。
意外ですが、この本はもし旅行の時に手に取っていたら感想が変わってたかもしれないなと思いました。旅行中なら「こういう考え方もあるんだって思いました。マネしたいと思いました」みたいなポジティブな感想になったと思います。
つまりだ。テンションが高いときに勢いで読むのに適しているってことです。一言一言かみ砕いて読むには不向きだ、と。悪い本ではないけど、ちょっと熱くなりすぎてしまった本なんだってことですね。
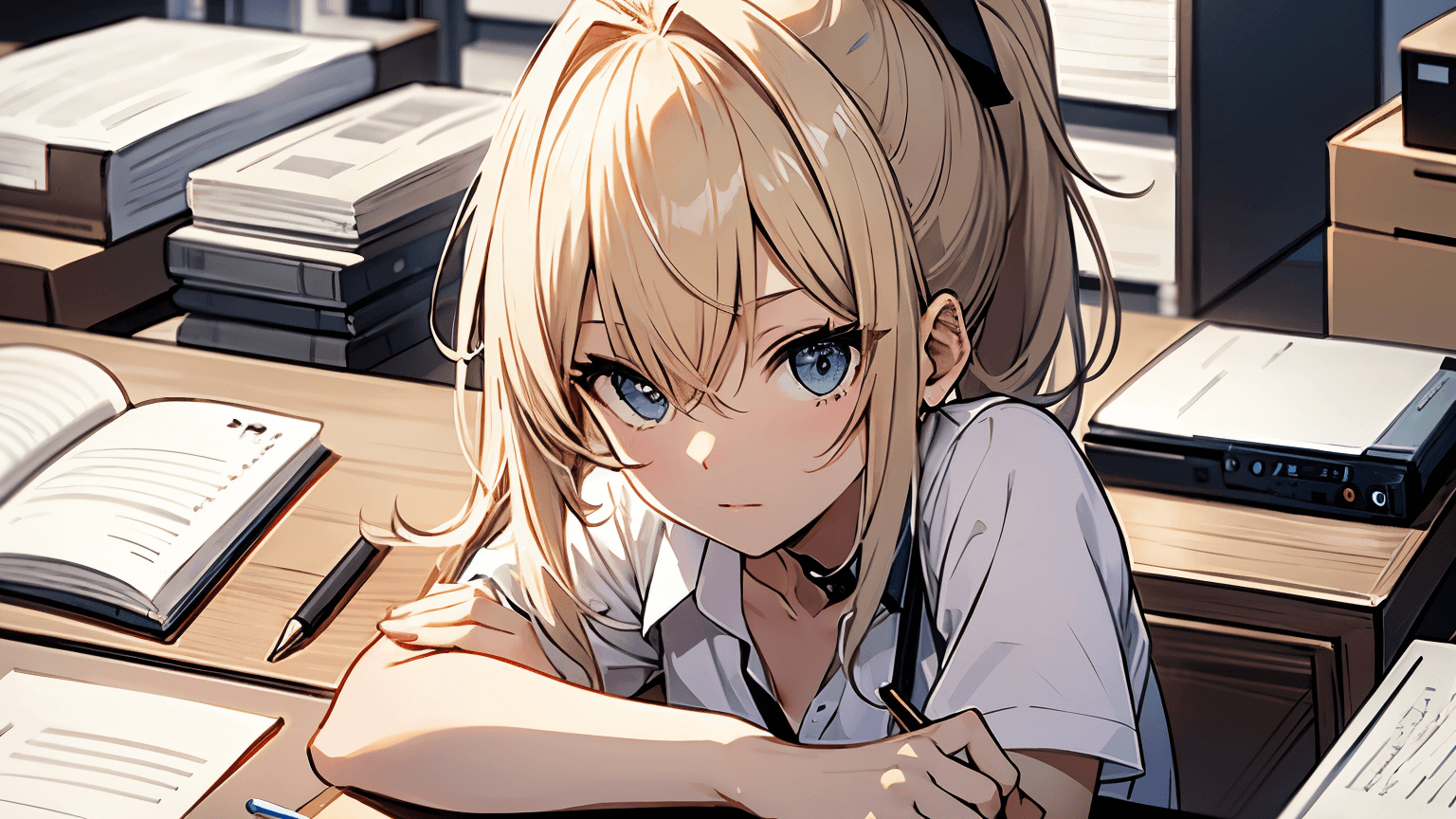


コメント